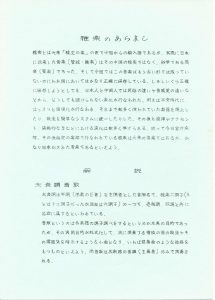楽理科クロニクル
本号より、70年以上にわたる楽理科の歴史をさまざまな角度からご紹介する 「楽理科クロニクル」の連載を開始しました。
初回は、1960年代初めの雅楽演奏会プログラムと、1980~2000年代の楽理科についてです。
「1960年代の雅楽演奏会プログラム」 ※プログラムは蒲
生郷昭氏提供のものです。
※画像はクリックすると拡大できます。
記憶をたぐって
蒲生郷昭
普通課程20名、教職課程5名というのが、そのころの定数でした。授業料は、真面目に勉強していれば6千円で済んだはずのところ、浪人したために9千円になっていました。育英会奨学金は、はじめは月額2千円で、2年生になったときでしたか、願い出て3千円に増額してもらい、大助かりでした。
大学院は、修士課程さえ設置されておらず、そのかわりに専攻科というのがありました。修了年限は、私が4年後そこに入る少し前に、1年から2年になったのだと思います。学部卒業後に進むところではありますが、大学院とは大違いで、修了しても何の資格も得られません。いまでも、各種の書類に最終学歴を書かされることがたびたびありますが、その都度、学部卒業を書くべきか専攻科修了を書くべきか、迷います。
入学式の日のことは、比較的鮮明に憶えています。といっても、式そのものではなく、終了後の話。楽理科の説明があるとのことで、奏楽堂の脇の2階の一室に集められました。ところがいくら待っても誰も説明に来てくれません。教務係長の伊藤さんがそれを知り、いぶかりながら浦和の服部先生のご自宅――現在のお宅とは違う――ヘ電話をしてくださると、なんと先生はご在宅。「すぐに行くからしばらく待つように」とのご指示でした。やがて始まったご説明で、服部先生は、時間割――たしかB5縦長縦組の一枚の紙でした――を利用して、その年の楽理科の授業を担当される先生がたを紹介してくださいました。当時は、水曜日に専門科目が集中していて、まず水曜日に出講の先生から始まったように記憶しています。最初は辻荘ー先生だったと思いますが、辻先生の場合は立教大学、野村良雄先生なら上智大学というように、別のところに本務をお持ちの先生が多いことがわかり、非常勤という制度をよく知らなかった私は、奇妙な印象を受けたものです。
机と椅子は教室によりいろいろで、かなり古そうなものもありました。私にとって印象が深いのは椅子で、お尻が乗るところが円形で――かつては籐だったのでしょうか――背もたれも曲線的に優美に作った、要するに古いけれどもとびきり洒落た椅子があったのです。高校・予備校までの”教室の椅子”のイメージとは、まったく異質のものでした。
当時は、大学のバッジとは別に、キタラに「楽」字を重ねた意匠の、音楽学部のバッジがありました。卒業後も、一つを大切にとっておいたのに、いつのまにか見えなくなりました。そのバッジが廃止されたので、なくしたのが残念でなりません。
「楽書講読」が英独仏だけだったころです。 カリキュラムには「邦楽概論」(当時、 町田嘉章先生のご担当)があるぐらいで、「日本音楽史」さえないという状態でした。そのため、岸辺成雄先生が、まったくのご好意で、昼休みを利用して「日本音楽史」を講じてくださるということがありました。大いに喜んだのですが、いきなり第1回が休講で拍子抜けしたのはともかく、次回の案内掲示を見落として、結局、一度も聴講しませんでした。その講義は、数回は行われたようです。
一学年上と一学年下の同好者諸氏と雅楽研究会を作ったのも、懐かしい思い出です。指導を東儀和太郎先生にお願いしましたが、林多美夫、東儀博、山田清彦の各先生も、手弁当で教えに来てくださいました。1961年にはクラブとして認知され、学友会はなにがしかの予算を計上してくれました。活動の盛り上がりを学内に顕示した、芸術祭での第1回発表会は、私にとっての貴重な、奏楽堂での演奏体験でもあります。曲は「越殿楽残楽三返」と「人長乙舞其駒」で、そのときの手作りのプログラム(ガリ切りは柘植元ー氏)によると、同年11月3日の12時30分開演でした。クラブは翌62年に「雅楽演習」という授業に昇格し、現在の「雅楽実技」に及びます。
音楽学部の構内には、大関さんのすぐそばに、たしか宮沢さんという靴屋の店もありました。ちょっと調子が悪い靴や汚れた靴を休み時間に預けると、授業中に、直したり、磨いておいてくれたりするのです。一足磨いてもらって30円だったでしょうか。私はずいぶん利用したものです。
学部卒業のときの謝恩会で写した記念写真があります。それを見ると、専門科目の岸辺成雄、小泉文夫、辻荘一、長谷川良夫、福田達夫、藤江効子、皆川達夫、渡部恵一郎の各先生と、外国語の秋山春水、佐藤覚、実吉捷郎の各先生、それに、所属が音楽資料係だった森節子先生が出席してくださっています。そのうち5人の先生は、お亡くなりになりました。級友も2人、亡くなっています。なお、ここに服部先生のお顔が見えないのは、フンボルト財団留学生として西ドイツに留学中でいらしたからです。
※
楽理科の19年間から
澁谷政子
私が楽理科に入学したのは1984年4月、0室助手を退任したのが2004年3月。その直後の2004年度に国立大学法人化がなされた。それ以降の変化はかなり大きくまたスピード感も伴うもので、それと比べれば、私が藝大にお世話になったこの19年間は、カリキュラムをはじめ楽理科をめぐる制度・状況は比較的安定していたと言えると思う。先輩も後輩も同じ体験を共有し、楽理科というカルチャーを受け継ぎ、豊かにしていった時期にあたるのではないだろうか。しかしそのなかでも、もちろん新たなページは開かれていったわけで、私の個人的な思いと記憶の範囲によるものではあるが、その幾つかを挙げさせていただこうと思う。
まず学部時代、私たちと同時に柘植元一先生と上参郷祐康先生が着任された。1年生の授業では土田英三郎先生の英語楽書の洗礼を受け、「あ〜もっと日本語で〜」という声が今でも耳に浮かぶ。我々の学年はそれぞれが思うままに動くようなクラスだったが、確か3年の学内演奏会で、ポーツマス・シンフォニア(楽器経験のない素人ばかりで演奏し、意図せぬ雑音、間違い、ずれ等が生じることを狙う)をやろう!ということになり、ベートーヴェンの「運命」をチョイス。指揮者は院生の野本由紀夫さんにしていただいた。しかし、いかにも楽理科らしく(?)真面目に練習をしてしまい、本番は「ただの下手くそなオーケストラ」(企画者・松本曜子さん談)になってしまった。当時は「現代音楽」が熱い時期で、1986年秋のサントリーホールのオープニング委嘱シリーズは私も含め多くの学生が聴きに行っていた。
同級の平井裕子さんが雅楽部を立ち上げたのも同じ頃だったと思う。芝祐靖先生の授業をとっていた私は彼女に半ば押し切られて鉦鼓係を仰せつかり、四芸祭で京都に演奏に行く道すがら、伊勢神宮や天理大学雅楽部を訪ねたことを印象深く覚えている。当時はまだ土曜日に授業があり、雅楽は午後、そして午前中は多田先生の通奏低音だった。授業については他にもいろいろと懐かしく思い起こされるが、単なる回想に逸れてしまいそうなので、このあたりで切り上げておく。
修士では、その頃の楽理では“標準”だった3年在籍の道を何の迷いもなく選んだ。それにしても、この「修士3年間」はいつ頃から慣習だったのだろうか?今振り返ってみると、なんと自由で贅沢な時間だったことか。現在では修士は博士への通過点的な位置づけが大きくなっていると思われるが、当時はほとんどの院生が修士論文で決着をつけるという姿勢で臨んでいた。
その後、非常勤助手や常勤助手、また博士後期課程院生として、出たり入ったりを繰り返したが、1994年度には0室常勤助手2名体制の最後を植村幸生さんと共に務めさせていただいた。この前後に、0室でファイルメーカーによる各種データベース構築やウェブ公開が動き出したのではないだろうか。1995年度からの院生RAの時期には、常勤の先生方から各分野の「基礎文献リスト」をいただきデータベース入力する作業があり、2002〜2003年度に再度常勤助手を勤めた際には、非常勤助手の方々と共に卒論・修論データベースの修正・公開の作業に携わった。
この0室勤務の2年間のうち、まず2002年は日本音楽学会創立50周年の記念大会の年でもあった。その基調講演を行ったニコラス・クック教授を迎え、細川周平さん、クリストフ・シャルルさんに加わっていただき、船山隆先生司会による同時通訳付きの豪華なシンポジウムが美校の中央講義棟で開催されたことはたいへん思い出深い。私事で恐縮だが、事務局の一員として準備に携わった50周年記念大会の成功と、留学時代の恩師との再会とが相まって、晴々とした気持ちのなかで、刺激的な講演やディスカッションに耳を傾けることができた。
そして2003年に「楽楽理会通信」1号(紙媒体)を発行。印刷業者から上がってきたモスグリーンを基調としたシンプルなレイアウト・デザインを目にして、うれしかったことを覚えている。多方面で活躍する方々を擁する同窓会の力により、卒業・修了後の学生の活躍を支援いただくことが今後必要になるということから発行に至った「通信」だが、その後ウェブ化され、そして今回寄稿させていただくことになり、ひときわ感慨深い。
結局、とりとめのない想い出雑記のようになってしまった。「クロニクル」の趣旨にお応えできているか自信はないが、いわば“work in progress”の種子の一つくらいにはなるだろうか。これから多くの方々が寄稿されていくなかで、追記、注記、修正、改編など加えていっていただければ幸いである。